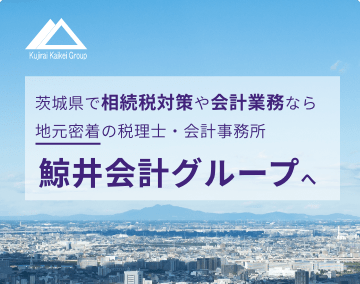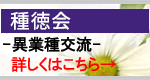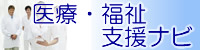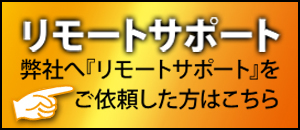コラム
公開日:2025/01/14
更新日:2025/01/14
遺言書で妻に全財産を相続させるのは可能?書き方は?遺留分は?

長年連れ添った妻にすべての遺産を相続させたいと考える方もいるでしょう。
そのような希望は、生前に遺言書を作成することで叶えることができます。
ただし、他の相続人にも法律上遺留分が保障されていますので、遺留分にも配慮した書き方をしなければトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。遺言書の書き方のポイントをしっかりと押さえて、トラブルのない遺産相続を実現できるよう準備を進めていきましょう。
今回は、遺言書で妻に全財産を相続させるための遺言書の書き方や遺留分について解説します。
1. 遺言書で妻に全財産を相続させることは可能か
そもそも遺言書で妻に全財産を相続させることは可能なのでしょうか。
(1)遺言書で妻に全財産を相続させることは可能
遺言内容は、法定の方式に従っている限り、遺言者が自由に決めることができます。自分自身の財産をどのように処分するかは、本人が自由に決められる事柄だからです。
そのため、遺言書で妻に全財産を相続させるという内容の遺言書であっても、法律上は有効な遺言として扱われます。
ただし、後述するような「遺留分」に配慮する必要がありますので注意が必要です。
(2)遺言書の種類
生前の相続対策で利用される遺言書(普通方式の遺言書)には、以下の3つの種類があります。このうち、主に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つになります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでも作成でき、費用もかからず遺言者一人で作成できる形式の遺言書ですので、手軽で自由度の高い遺言書といえるでしょう。
ただし、遺言書には、民法上厳格な要件が定められていますので、一つでも要件を欠いてしまうと、遺言書全体が無効になってしまいますので、法律の専門家に確認しながら作成するのがおすすめです。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要で、公証人に支払う手数料が必要になるなど手間と費用がかかるという点がデメリットとして挙げられます。
しかし、専門家である公証人が作成に関与しますので、方式の不備により遺言書が無効になるリスクはほとんどなく、公証役場で遺言書が保管されるため紛失、偽造のリスクもありません。
そのため、遺言内容を確実に実現したいときは、公正証書遺言の利用がおすすめです。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場においてその存在を証明する遺言書です。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密することができるというメリットがありますが、公証人は内容面をチェックできませんので、遺言書の不備により無効になるリスクがあります。
また、作成後の遺言書は、遺言者が保管しなければなりませんので、紛失・偽造のリスクもあります。
手間と費用がかかるわりにメリットが少ないため、実務ではほとんど利用されていない遺言書になります。
2. 妻に全財産を相続させる自筆証書遺言の書き方
(1)妻に全財産を相続させる自筆証書遺言の記載例
遺言書
遺言者○○は、次のとおり遺言する。
1、遺言者は、遺言者の有するすべての遺産を妻○○(昭和○年○月〇日生)に相続させる。
付言事項
私が亡くなった後、妻がお金や住まいの心配をせずに、安心して老後を過ごせるようにすべての遺産を相続させることにしました。長男○○と長女○○には、お母さんが安心して暮らせるように、遺留分の請求をしないようお願いします。家族で仲良く助け合って暮らすことを願っています。令和○年○月〇日
東京都○○区○○1丁目1番1号
○○○○㊞
(2)書き方のポイント
妻に全財産を相続させる遺言書を作成する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
①付言事項を記載する
付言事項とは、遺言に記載しても法的効力を持たない記載事項をいいます。遺言書に絶対に書かなければならない事項ではありませんが、遺言作成の経緯、遺言者の気持ち、家族への感謝のメッセージなどを記載することでトラブル防止に役立ちます。
全財産を妻に相続させる遺言だと、他の相続人の取り分が一切なくなるため、不満が出る可能性があります。
そのため、なぜそのような遺言を作成したのかを付言事項で残しておくことで、他の相続人の納得が得られやすいといえます。
②財産目録を作成する
妻に全財産を相続させる場合、「すべての遺産を相続させる」とだけ記載すれば足り、財産を特定する必要はありません。
しかし、遺産を相続した妻が遺産の全容を把握していない場合、遺産の調査をしなければならない負担が生じてしまいます。
妻の負担を少しでも減らすためにも、財産目録を作成して、遺言書の別紙として添付するのがおすすめです。
3. 妻に全財産を相続させる遺言書と遺留分の関係
妻に全財産を相続させる遺言書を作成する場合には、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。
(1)遺留分とは
遺留分とは、一定の範囲の相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取得割合をいいます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に対して、以下のような割合で認められています。
- 相続人が直系尊属のみの場合……法定相続分の3分の1
- それ以外の場合……法定相続分の2分の1
(2)遺言書であっても遺留分は侵害できない
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、法定の方式を満たしている限りは、有効な遺言書として扱われます。
しかし、遺留分は、被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度ですので、遺言書であっても遺留分を奪うことはできません。
そのため、遺言書により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
なお、遺留分侵害額請求には期限があり、相続開始および遺留分侵害を知ってから1年または相続開始から10年が経過すると時効(除斥期間)により権利が失われてしまいます。
(3)遺留分に十分配慮して遺言書を作成する必要性
このように相続人には遺留分が保障されていますので、妻に全財産を相続させる遺言だと遺留分を侵害してしまいます。
遺留分によるトラブルを避けるのであれば、最低限の遺留分については妻以外の相続人に行き渡るような遺言内容に変更した方がよいでしょう。
どうしても妻に全財産を相続させたいのであれば、生前に家族に事情を説明して納得してもらうか、付言事項で遺言書作成の経緯を記載すべきでしょう。
ただし、付言事項には法的効力はありませんので、付言事項で遺留分の請求をしないよう求めたとしても、遺留分侵害額請求を防ぐことはできませんので注意が必要です。
4. まとめ
妻に全財産を渡す内容の遺言書を作成することは可能ですが、他にも相続人がいる場合には、他の相続人の遺留分を侵害してしまいます。
遺留分によるトラブルを回避するには、遺留分に配慮した内容の遺言にするか、付言事項を活用することが有効です。
また、相続税と贈与税などについては、税理士にご相談ください。
当事務所でも、税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせて頂いております。お気軽にご相談ください。