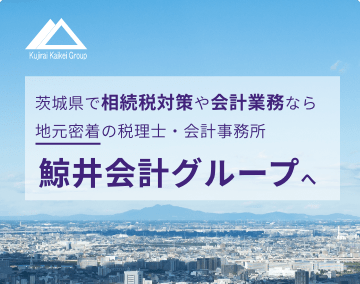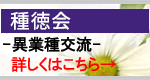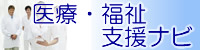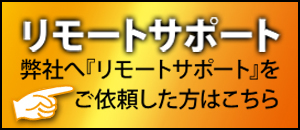コラム
公開日:2025/01/14
更新日:2025/01/14
亡くなった人の預金を少額おろすには?おろすのは罪ではない?

被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、被相続人の預貯金口座は凍結されてしまいます。
口座が凍結されてしまうと被相続人の葬儀費用や入院費用などを被相続人の預貯金から支払うことができなくなってしまいますので、凍結前に預貯金をおろそうとする方もいるでしょう。
このような亡くなった人の預貯金をおろす行為は、犯罪になるのでしょうか。また、適法に預貯金を少額おろすにはどのような方法があるのでしょうか。
今回は、亡くなった人の預貯金をおろす方法についてわかりやすく解説します。
1. 亡くなった人の預金を凍結前に下ろすと罪になる?
そもそも亡くなった人の預金を凍結前におろすと罪になるのでしょうか。
(1)亡くなった人の預金を下ろしても刑事事件になる可能性は低い
結論から言うと亡くなった人の預金をおろしたとしても、刑事事件になる可能性は低いです。
なぜなら、刑法には「親族相盗例」という特例があり、家庭内の財産上の問題(窃盗、横領など)については、刑が免除されることになっているからです。
このように亡くなった人の預金の引き出しは、刑事事件として問題になることはほとんどありませんが、後述するように民事上のトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。
(2)民事上のトラブルになる可能性
亡くなった人の預金は、遺言書がない限り、相続開始と同時に相続人全員の共有となります。
そのため、亡くなった人の預金をおろすためには原則として遺産分割協議が成立してからでなければできず、勝手に預貯金をおろすのは民事上のトラブルになる可能性があります。
特に、自己の法定相続分を超えて預金の引き出しをすると、他の相続人の権利を侵害することになりますので、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求を受けるリスクがありますので注意してください。
(3)相続放棄できなくなる可能性
亡くなった人の預金を下ろす行為は、法定単純承認事由の一つである「相続財産の全部または一部の処分」に該当する可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為があると相続放棄や限定承認ができなくなってしまいますので、被相続人に多額の借金があったとしてもそれを引き継がなければなりません。
相続放棄を予定している人は、亡くなった人の預金をおろしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、預金をおろすのは避けた方がよいでしょう。
2. 亡くなった人の口座から預貯金を下ろすには
亡くなった人の口座から預貯金をおろすと民事上のトラブルになる可能性がありますが、以下のような法律上の制度に基づいて預金をおろせばそのようなトラブルを回避できます。
以下では、亡くなった人の口座から遺産分割前に適法に預金を下ろす2つの方法を説明します。
(1)預貯金の仮払い制度での引き出し
預貯金の仮払い制度とは、被相続人が亡くなり相続が開始した後に、法定相続人が被相続人の預貯金を一定の範囲内で払い戻すことができる制度です。預貯金の仮払い制度は、民法改正により2019年7月1日から適用が開始された比較的新しい制度となっています。葬儀費用などでお金が必要な場合には、預貯金の仮払い制度を利用することで適法に亡くなった人の口座から預貯金を下すことが可能です。
預貯金の仮払い制度では、口座から引き出すことができる預貯金には限度額が設けられており、①または②の金額のうちいずれか低い方の金額までとなります。
- ①死亡時の預貯金残高×その相続人の法定相続分×1/3
- ②150万円
ただし、出金額の上限は、金融機関ごと設定されていますので、複数の金融機関に口座を有している場合は、金融機関ごとに仮払い制度を利用すれば、出金できる金額を増やすことができます。
なお、預貯金の仮払い制度を利用する際に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・預貯金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書および本人確認書類
(2)預貯金債権の仮分割の仮処分
預貯金の仮払い制度は、引き出せる金額に上限があるため、上限まで引き出しても不足するような場合は、家庭裁判所の預貯金債権の仮分割の仮処分という手続きを利用するとよいでしょう。
預貯金債権の仮分割の仮処分とは、家庭裁判所の保全処分により遺産分割前に預貯金を引き出すことができる制度です。預貯金債権の仮分割の仮処分が認められれば、法定相続分の範囲内で預貯金を引き出すことが可能になります。
以前は、「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳格な要件が設けられていたため、簡単には利用できない制度でしたが、民法改正により2019年7月1日から要件が緩和されましたので利用しやすい制度になっています。
なお、同制度を利用する際の必要書類は、以下のとおりです。
- 申立書
- 戸籍、住所関係書類
- 遺産内容に関する書類
- 仮分割の必要性に関する資料(金融機関発行の民法909条の2に基づく払戻しの証明書、申立人・同居家族の収入・家計収支資料、報告書、陳述書など)
3. 凍結された被相続人の口座を相続する方法・必要書類
凍結された被相続人の預貯金を相続するにはどうすればよいのでしょうか。以下では、凍結された被相続人の預貯金を相続する方法と必要書類を説明します。
(1)凍結された口座の預貯金を相続する方法
凍結された口座の預貯金を相続する方法には、以下の3つの方法が考えられます。
①遺産分割協議
凍結された口座の預貯金を相続するには、まずは相続人による遺産分割協議を行う必要があります。
相続人による遺産分割協議が成立すれば、その内容に基づいて凍結された口座の預貯金を相続することができます。
②遺産分割調停
相続人による遺産分割協議では遺産の相続方法などが決まらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割調停で話し合いがまとまれば調停成立となり、その内容に基づいて凍結された口座の預貯金を相続することができます。
③遺産分割審判
遺産分割調停でも話し合いがまとまらないときは、調停不成立となり自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。
遺産分割審判では、調停での一切の事情や当事者からの主張立証を踏まえて、裁判官が適切な遺産分割方法を決定します。審判が確定すれば、その内容に基づいて凍結された口座の預貯金を相続することができます。
(2)凍結された口座から相続した預貯金を下ろすための必要書類
凍結された口座から相続した預貯金をおろす場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 預金名義変更依頼書(金融機関所定の様式)
- 被相続人の通帳およびキャッシュカード
- (遺産分割協議の場合)遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本
- (遺産分割調停の場合)調停調書謄本
- (遺産分割審判の場合)審判書謄本、審判確定証明書
4. まとめ
亡くなった人の預貯金を遺産分割前におろす行為自体は犯罪にあたる可能性は低いですが、民事上のトラブルになる可能性があります。
このようなトラブルを回避するには、預貯金の仮払い制度または預貯金債権の仮分割の仮処分といった法的制度を利用するとよいでしょう。
ただし、当該制度を利用して預貯金をおろしてしまうと相続放棄ができなくなるといったリスクも生じますので、まずは専門家に相談して今後の方針についてアドバイスしてもらうようにしましょう。
また、相続税と贈与税などについても、法律の専門家にご相談ください。
当事務所でも、税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせて頂いております。お気軽にご相談ください。