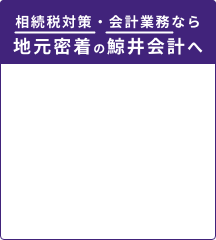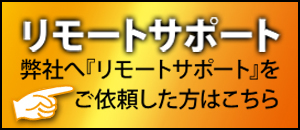コラム
公開日:2022/10/11
更新日:2022/10/11
特別受益とは|判断基準・持ち戻し免除・生前贈与との違い等を解説

相続人が受けた遺言による贈与(遺贈)や生前贈与は、遺産分割において「特別受益」として取り扱われます。特別受益がある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えることで、相続人間の公平が図られます。
特別受益については、計算方法や持ち戻し免除、生前贈与との違い、特別受益に当たらない生前贈与はあるか、相続税申告などとの関係で注意すべきポイントがありますので、弁護士に相談しながら適切に遺産分割を進めてください。
今回は、遺産分割において問題となる特別受益について詳しく解説します。
1. 特別受益とは
特別受益とは、相続人が亡くなった被相続人から特別に受けた遺贈や贈与です。遺産分割では「持ち戻し計算」により、特別受益のある相続人とそれ以外の相続人の間で、相続分の調整が行われます。
1-1. 特別受益を認める目的
遺産分割において特別受益を考慮するのは、相続人間の公平を図るためです。
一部の相続人だけが遺贈や贈与を受けた場合、他の相続人との間で取得できる財産額に格差が生じてしまいます。そこで、すべての相続人の相続に対する合理的な期待を保護し、公平な遺産分割を実現するため、特別受益による相続分の調整が行われるのです。
なお、特別受益は相続人間の公平を図る制度であるため、相続人以外の者に対して行われた遺贈や贈与は、特別受益に該当しません。
1-2. 特別受益に該当する遺贈・贈与
特別受益に該当するのは、以下の遺贈・贈与です(民法903条1項)。
①遺贈
すべての遺贈が特別受益に該当します。
②贈与(死因贈与・生前贈与)
以下のいずれかに該当する贈与が特別受益に該当します。
- (a)婚姻のための贈与
- →結納金、結婚持参品の購入費用など
- (b)養子縁組のための贈与
- →養子に持たせた持参金など
- (c)生計の資本としての贈与
- →生活費の援助、子どもの学費の援助、新居の購入費用など(*例外あり、以下解説)
1-3. 特別受益に当たらない生前贈与
なお、特別受益イコール生前贈与と考えている方もいますが、違いがあります。特別受益に当たらない生前贈与もあるからです。
例えば、生活費については、扶養義務の範囲内と認められる場合は、特別受益である「生計の資本としての贈与」に該当しません。
特別受益となるのは、あくまでも扶養義務の範囲を超えて特別に行われた贈与に限られます。このように特別受益に当たらない生前贈与もあるため、遺産分割する際には注意が必要です。
2. 特別受益の持ち戻しとは
一部の相続人に特別受益がある場合、原則として特別受益の「持ち戻し」を行い、各相続人の相続分を計算します。
2-1. 特別受益は遺産分割の際に持ち戻すのが原則
特別受益の「持ち戻し」計算とは、特別受益に当たる遺贈や贈与の対象財産が相続財産に含まれると仮定して、各相続人の相続分を計算することを意味します(具体的な計算方法は後述)。
被相続人による特段の意思表示がなければ、遺産分割において特別受益の持ち戻し計算を行うのが原則です。
なお、遺産分割の際に持ち戻す特別受益が、贈与の時期によって限定されることはありません。したがって、何十年も前に行われた生前贈与であっても、法的には特別受益として持ち戻し計算を行う必要があります。
2-2. 被相続人の意思表示により、特別受益の持ち戻しは免除可能
ただし、遺産分割において被相続人の意思を尊重する観点から、特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示によって免除することが認められています(民法903条3項)。
持ち戻し免除の意思表示については、特に方式は定められていません。遺言書による場合が多いですが、それ以外の書面や口頭による持ち戻し免除も認められます。
2-3. 婚姻期間20年以上の場合、自宅の贈与については持ち戻し免除が推定される
被相続人が、婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用建物とその敷地を遺贈・贈与した場合、当該遺贈・贈与については持ち戻し免除の意思表示が推定されます(民法903条4項)。
被相続人と長年連れ添った配偶者が、遺産分割の争いを経ることなく住居を確保できるようにするためです。
ただし、あくまでも「推定」であるため、被相続人が明示的に異なる意思表示をした場合には、その意思表示に従います。
具体的には、遺言書その他の書面などにおいて「配偶者に対する居住用建物・敷地の贈与については、特別受益の持ち戻しを免除しない」と明記されていれば、特別受益の持ち戻し計算を行う必要があるということです。
3. 特別受益の金額・持ち戻し計算の例
特別受益の金額を算定する際には、基準時や滅失・価格の増減に関する取扱いに注意が必要です。
実際の持ち戻し計算の例と併せて、遺産分割において特別受益がどのように取り扱われるのかを見てみましょう。
3-1. 特別受益の基準時は相続開始時
特別受益の基準時は、相続開始の時点(=被相続人が死亡した時点)であると解されています。
特別受益の持ち戻しの基本的な考え方は、「遺贈・贈与の目的財産が、現存する相続財産に含まれていると仮定する」というものです。
そのため、贈与時と相続開始時で特別受益に当たる財産の価値が異なる場合には、相続開始時の価値を特別受益の金額として採用します。
ただし例外的に、受贈者である相続人の行為により、特別受益の目的財産が滅失し、またはその価格が増減した場合には、滅失・価格の増減がなかったものとして特別受益の金額を計算します(民法904条)。
- (例)
- 特別受益に当たる贈与により取得した居住用建物を、受贈者が失火によって滅失させた場合
- →居住用建物が存在すると仮定して、相続開始時における価値を特別受益とする
- 特別受益に当たる贈与により取得した居住用建物に、受贈者が増改築を加えた場合
- →増改築がなかったものと仮定して、相続開始時における価値を特別受益とする
3-2. 特別受益の持ち戻し計算の例
以下の設例を用いて、特別受益の持ち戻し計算の例を紹介します。
- <設例>
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 相続財産は6000万円分
- Bには1200万円の特別受益あり
まず、現存する相続財産を法定相続分に従って分割すれば、以下の配分となります。
- <特別受益を考慮しない相続分>
- A:3000万円
- B:1500万円
- C:1500万円
しかし、Bはすでに1200万円の特別受益を受けているため、上記ではBがもらいすぎとなってしまいます。
そこで、特別受益の持ち戻し計算を行います。まず、現存する相続財産と特別受益を合わせた7200万円につき、相続分を再計算します。
- A:3600万円
- B:1800万円(特別受益1200万円を含む)
- C:1800万円
Bの相続分から特別受益を控除すると、以下のとおり実際の相続分を求めることができます。
- <特別受益を考慮した相続分>
- A;3600万円
- B:600万円
- C:1800万円
特別受益を考慮しない場合と比べると、特別受益のあるBの相続分は減少し、反対にA・Cの相続分は増加しました。
このように、特別受益の持ち戻し計算を行うことで、特別受益のある相続人とそれ以外の相続人の間で公平を図ることができます。
4. 相続税申告における特別受益の取扱い
特別受益に当たる遺贈・贈与については、相続税の課税対象になる場合とならない場合があります。
課税対象となる特別受益については、相続税申告を行う際に漏れなく申告を行ってください。
4-1. 相続税の課税対象となる特別受益
相続税の課税対象となる主な特別受益は、以下のとおりです。
- 遺贈
- 死因贈与
- 相続開始前3年以内に行われた生前贈与
- 相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与など
上記のいずれかに該当する特別受益は、相続財産と併せて相続税申告を行わなければなりません。
4-2. 相続税の課税対象ではない特別受益
これに対して、特別受益に当たる生前贈与のうち、相続開始の3年超前に行われ、かつ相続時精算課税制度の適用を受けていないものについては、相続税の課税対象ではありません。
ただし、相続税の課税対象ではない生前贈与は、贈与税の課税対象となります。したがって本来であれば、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告を行い、贈与税を納付しなければなりません。
もし贈与税を納付していない場合、税務調査の際に追徴課税を受ける可能性がある点にご注意ください。
5. まとめ
特別受益がある場合において、相続分を正しく計算したうえで適切に遺産分割を行うためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
相続税・贈与税の申告・納付についても、税理士と連携していればワンストップでご相談いただけます。
遺産分割における特別受益の取扱いに迷った場合、持ち戻しの免除を行いたい場合、特別受益に当たる生前贈与か、当たらない生前贈与かどうか分からない場合等には、法律の専門家にご相談ください。
当事務所でも、税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせて頂いております。お気軽にご相談ください。