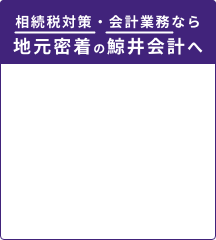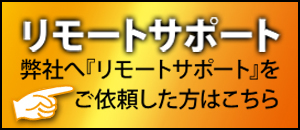コラム
公開日:2022/12/06
更新日:2022/12/06
遺産相続と遺留分|割合や計算方法、時効などをわかりやすく解説

兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。
遺言書や生前贈与の結果、ご自身の取得する遺産額が遺留分未満に抑えられてしまった場合には、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
今回は、遺産相続の場面で問題となる遺留分とは何か、計算方法や割合はいくらか、時効はあるか、法定相続分との違いは何か、基本的な知識をわかりやすく解説します。
1. 遺留分とは
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。遺留分を下回る遺産しか取得できなかった方は、遺留分侵害額請求(後述)を行うことができます。
1-1. 遺留分の目的|また、遺言との関係
遺留分の制度が設けられているのは、わかりやすく言うと、法定相続人の相続に対する期待を保護するためです。
被相続人が自分自身の財産をどのように処分するかについては、被相続人が自分自身で決めるべき事柄です。そのため、遺言書や生前贈与により、被相続人の判断で財産を譲り渡すことが認められています。
その一方で、遺産を相続できると思っていたのに、いざ相続が発生して遺言書を確認してみたら、全く遺産をもらえないことになっていた……というのは、法定相続人にとって酷な面があります。
そこで、被相続人の意思と法定相続人の期待のバランスを取って、法定相続分のうち一定の割合に限り遺留分が認められているのです。
1-2. 遺留分と法定相続分の違い
遺留分は法定相続人に認められた具体的な権利であり、侵害された場合には他の相続人などに対して金銭の支払いを請求することが可能です。
これに対して法定相続分は、相続できる遺産の割合に関する目安に過ぎません。
遺産分割協議・調停では、相続人全員の合意により、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することもできます。
遺産分割審判では、基本的に法定相続分を基準として分割方法が示されますが、絶対的な基準というわけではありません。
ただし、遺留分割合(遺留分額)は法定相続分を基に計算されます。そのため法定相続分も、遺留分の範囲では具体化された権利であると評価できるでしょう。
2. 遺留分が認められる相続人の範囲|兄弟は?
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母など)に遺留分が認められます。
なお、被相続人の子が死亡・相続欠格(民法891条)・相続廃除(民法892条)によって相続権を失った場合、さらにその子(被相続人の孫)が「代襲相続人」となります(民法887条2項)。
また、被相続人のひ孫以降も代襲相続人となる場合があります(再代襲相続、同条3項)。
代襲相続人については、被代襲者(死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った人)と同等の遺留分が認められます。
3. 遺留分侵害額の計算方法
実際に取得した遺産額が遺留分額に満たない場合、その差額を「遺留分侵害額」といいます。遺留分侵害額の計算方法は、以下わかりやすく解説します。
3-1. 相続財産等の総額を計算する
まず、遺留分の基礎となる財産の総額を計算します。遺留分の基礎財産に含まれるのは、以下の財産です(民法1043条~1045条)。
(1)相続財産
被相続人が死亡時に有した財産です。なお、債務がある場合にはその金額を控除します。
(2)遺贈された財産
遺言によって贈与された財産です。負担付遺贈の場合は、負担の価額が控除されます。
(3)相続開始前の一定期間に贈与された財産
相続人に対する生前贈与については、相続開始前10年間に行われたものが算入されます(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限られます)。
相続人以外の者に対する生前贈与については、相続開始前1年間に行われたものが算入されます。
なお、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定めます(民法1043条2項)。
(4)「総額」の例
- (例)
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 相続財産が2,000万円
- 遺贈された財産が1,000万円
- Bに対して4年前に贈与された財産が1,000万円
- 妹Dに対して2年前に贈与された財産が500万円
→遺留分の基礎財産は4,000万円(妹Dに対して2年前に贈与された500万円は含まれない)
3-2. 遺留分割合を計算する
次に、以下の要領で遺留分割合を計算します(民法1042条1項)。
(1)直系尊属のみが相続人の場合
・法定相続分の3分の1
(2)それ以外の場合
・法定相続分の2分の1
(3)「遺留分割合」の例
- (例)
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
→法定相続分はAが2分の1、BとCが4分の1ずつ
したがって、遺留分割合はAが4分の1、BとCが8分の1ずつ
3-3. 遺留分額を計算する
遺留分の基礎財産に遺留分割合を掛けて、遺留分額を計算します(計算式:基礎財産×遺留分割合=遺留分額)。
- (例)
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 遺留分の基礎財産は4,000万円
→遺留分割合はAが4分の1、BとCが8分の1ずつ。したがって、遺留分額はAが1,000万円、BとCが500万円ずつ
3-4. 遺留分額から実際の取得額を控除する
遺留分額から、基礎財産のうち実際に取得した財産の額を控除して、遺留分侵害額を計算します(計算式:遺留分侵害額=遺留分額-実際の取得額)
- (例)
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 遺留分の基礎財産は4,000万円
- 基礎財産のうち、AとBは1,900万円ずつ、Cは200万円を取得
→遺留分額はAが1,000万円、BとCが500万円ずつ。Cは基礎財産のうち200万円しか取得していないので、Cの遺留分侵害額は300万円
4. 遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」
遺留分侵害額については、遺留分の基礎財産を多く取得した者に対して支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます(民法1046条1項)。以下わかりやすく解説します。
4-1. 不足分について金銭を請求可能
遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める請求です。
たとえば不動産の遺贈によって遺留分侵害が発生した場合、不動産を相続財産に戻させるのではなく、不動産を取得した人が遺留分侵害額に相当する金銭を支払う形で解決します。
以前は金銭の支払いではなく現物返還が原則とされていましたが、2019年7月1日施行の改正民法によってルールが変更され、現在の金銭請求の形となりました。
4-2. 遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額は、以下の順位に従って、上位の者から順に負担します(民法1047条1項)。なお、同時に贈与を受けた者の間では、贈与価額に応じて遺留分侵害額を負担します。
- (1)受遺者(相続によって財産を取得した人、または遺贈を受けた人)
- (2)受贈者(生前贈与を受けた人。後に贈与を受けた人の方が上位)
ただし、相続人が遺留分侵害額を負担する場合は、相続人自身の遺留分が侵害されない範囲内に限られます。
- (例)
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 遺留分の基礎財産は4,000万円
- 基礎財産のうち、Cは200万円を取得。AとBは、それぞれ以下の時期に総額1,900万円ずつを取得
- – 相続開始の5年前の生前贈与によって、Bは900万円を取得
- – 相続開始の2年前の生前贈与によって、Aは400万円を取得
- – 相続によってAは1,500万円、Bは1,000万円を取得
→遺留分額はAが1,000万円、BとCが500万円ずつ。Cは基礎財産のうち200万円しか取得していないので、Cの遺留分侵害額は300万円。
遺留分侵害額を負担するのは、受遺者(相続によって財産を取得した人)であるAとB。相続の金額(A:1,500万円、B:1,000万円)に応じて遺留分侵害額を負担するため、Aの負担額は180万円、Bの負担額は120万円
したがってCは、Aに対して180万円、Bに対して120万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。
4-3. 遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また同様に、相続開始の時から10年を経過した場合も、遺留分侵害額請求権は時効消滅してしまいます(民法1048条)。
遺留分侵害額請求権の時効完成を阻止するには、時効の「完成猶予」または「更新」の手続きを取る必要があります。
- 時効の完成猶予:時効期間が経過しても、時効の完成を一時的に阻止すること
- 時効の更新:時効期間をリセットすること
- <時効の完成猶予事由>
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 和解
- 調停
- 倒産手続参加
- 強制執行
- 担保権の実行
- 競売
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
- 仮差押え、仮処分
- 内容証明郵便などによる履行の催告(6か月間のみ)
- 協議の合意
- <時効の更新事由>
- 裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加の後で権利が確定したこと
- 強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続が終了したこと
- 権利の承認
遺留分侵害額請求権の時効期間は1年と短いので、弁護士に相談して早めに対応することをお勧めいたします。
5. まとめ
今回は遺留分とは何か、その計算方法や割合、いくらぐらいになるのかの例、時効はあるのか、法定相続分との違いなどをわかりやすく解説しました。
遺留分については、法律の専門家にご相談ください。
当事務所でも、税理士・弁護士・社労士・司法書士・不動産鑑定士・FP等と連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせて頂いております。お気軽にご相談ください。